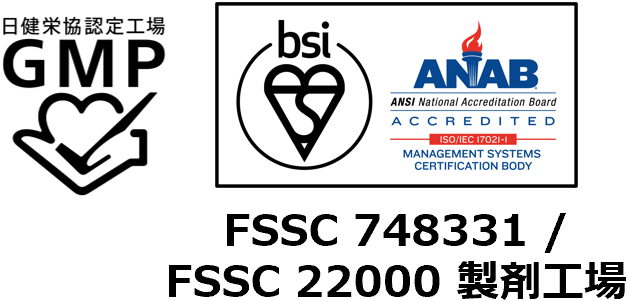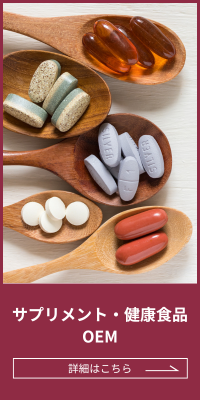#差別化
2025.07.11
機能性表示食品と栄養機能食品の違いとは?

健康志向の高まりとともに、ドラッグストアなどでは「機能性表示食品」や「栄養機能食品」といった表示が付いている健康食品を目にする機会が増えました。どちらも健康維持や体調管理を目的とした食品ですが、その制度や表示の仕組みには明確な違いがあります。この記事では、そんな機能性表示食品と栄養機能食品の違いを解説します。
そもそも「機能性表示食品」と「栄養機能食品」とは?
「機能性表示食品」と「栄養機能食品」は、どちらも特定の健康効果を伝えることができる「保健機能食品」のひとつですが、その制度の仕組みや表示の方法に違いがあります。まずは、それぞれがどのような制度なのかを見ていきましょう。
機能性表示食品とは?
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて「お腹の調子を整える」や「目の健康をサポート」など、健康への具体的な機能を表示できる食品のことです。国の審査はありませんが、事業者が安全性の情報や機能性に関する科学的根拠を集め、その情報を消費者庁に届け出る必要があります。届け出た情報は一部を除き、消費者庁のHPに公開されているので、消費者にとって透明性の高い食品と言えます。
栄養機能食品とは?
栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなどの栄養素の補給・補完を目的とした食品で、一定の成分量を満たしていれば国への申請や届出なしで販売できる食品です。例えば、「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」といった表現が可能になります。表示できる機能性の文言は定型文のみですが、比較的スピーディーに製品化できるのが特徴です。
機能性表示食品と栄養機能食品の主な違い
では、具体的に機能性表示食品と栄養機能食品の主な違いについて見ていきましょう。
国による審査の有無
機能性表示食品は、消費者庁への届出が必要ですが、国が個別に審査・認可を行うわけではありません。一方、栄養機能食品は、成分量や表示のルールが定められており、企業がその基準を満たせば、届出や審査不要で販売できます。この点で、栄養機能食品のほうが開発にかかる負担は軽いと言えます。
対象となる成分
栄養機能食品で使用できる成分は、ビタミンやミネラルなど、国が定めた栄養素に限定されています。一方、機能性表示食品では、より幅広い成分(食物繊維・アントシアニン・乳酸菌など)を対象に、 様々な機能性を訴求できます。製品の設計自由度は、機能性表示食品のほうが高くなります。
消費者への情報開示の内容
機能性表示食品では、届出情報や科学的根拠、機能性の詳細が消費者庁のサイト上で公開されます。そのため、消費者も購入前に機能の根拠を確認することができます。栄養機能食品は、詳細な情報開示の義務はありません。
健康食品をつくる際、機能性表示食品と栄養機能食品のどちらがいい?
機能性表示食品と栄養機能食品のどちらをつくるべきかお悩みの方は、その製品の目的や開発コスト、法規制・リスクの許容度に応じて選ぶとよいでしょう。
開発コストとスピードで選ぶ
栄養機能食品は、国の定めた成分と表示ルールに沿っていれば、開発製造に際して届出が不要です。そのため、短期間・低コストで商品化することができます。一方、機能性表示食品は、科学的根拠の準備や届出書類の作成が必要なため、開発に時間とコストがかかります。スピード重視なら栄養機能食品がおすすめです。
法規制やリスクの許容度で選ぶ
機能性表示食品は、自社責任で表示内容を裏付ける必要があるため、法的リスクの管理も求められます。表示ミスや根拠不足があれば行政指導を受ける可能性もあります。一方で、栄養機能食品は規定が明確で審査も不要なため、リスクを抑えながら開発製造できます。法規制に不慣れな企業には扱いやすいと言えます。
備前化成では機能性表示食品の開発製造から届出までサポート可能
備前化成では、機能性表示食品のOEM製造を検討している企業様向けに、開発から届出、製造、品質管理までを一貫してサポートしています。専門スタッフが科学的根拠の整理や書類作成をサポートするため、煩雑な届出業務も安心して行うことができます。
また、健康食品GMPやFSSC22000などの認証も取得しており、安全に健康食品を開発製造できる体制を整えています。高品質な製造体制や豊富な原料・処方の提案力も強みです。初めて機能性表示食品を扱う企業様でもスムーズに商品化が可能で、安心して市場投入まで進めることができます。
まとめ
機能性表示食品と栄養機能食品は、どちらも健康食品の制度として確立されていますが、審査や表示内容、対象成分などに大きな違いがあります。開発スピードやコスト、リスク対応などの観点から、自社に合った健康食品をつくることをおすすめします。