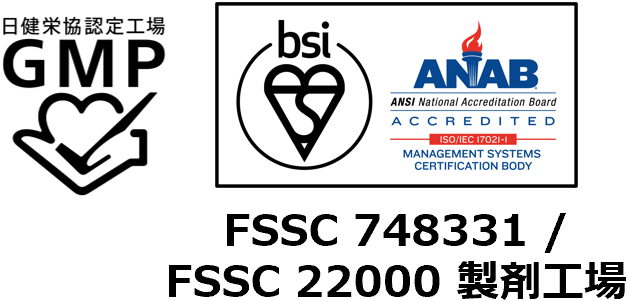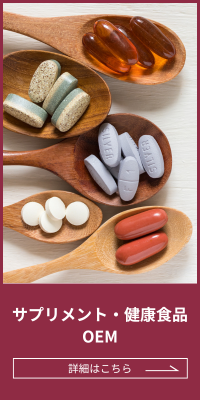#製造
2025.03.27
プロテインの製造方法とは?基礎知識や最終製品化までのステップを解説

プロテインの製造方法を知りたい方に向けて、本記事では、プロテイン製造に関する基礎知識を網羅的に解説しています。プロテインの種類や原料、製品形態の選び方、OEM製造のメリット、製造の流れ、そして信頼できるOEMメーカーの選び方まで、プロテイン製造に関わるあらゆる疑問を解消し、あなたの課題解決を支援します。
プロテイン製造の基礎知識
プロテイン製造の基礎知識として、原料と製品の種類について解説します。
プロテイン原料の主な種類
- ホエイプロテイン
ホエイプロテインは、牛乳から乳清(ホエイ)を分離・精製して作られる水溶性でクセが少ない動物性タンパク質です。吸収が速く、筋肉の修復・成長に優れた効果を発揮するため、特に運動後の摂取に適しています。ホエイプロテインには、精製度の違いによってWPC(濃縮ホエイ)、WPI(分離ホエイ)、WPH(加水分解ホエイ)の3種類があり、それぞれタンパク質含有量や吸収速度が異なります。乳糖不耐症の人を考慮した製品づくりなら、乳糖が少ないWPIやWPHを選ぶと良いでしょう。
- カゼインプロテイン
カゼインプロテインは、ホエイと同じく牛乳由来ですが、不溶性で吸収速度が遅いのが特徴です。胃の中でゲル化し、ゆっくりとアミノ酸を放出するため、長時間にわたって筋肉に栄養を供給できるので、就寝前や食事と食事の間の摂取に適しています。また、カゼインプロテインには、筋肉の分解を防ぐ効果があり、ダイエット中や筋肉を維持したい人にも適しています。カゼインは牛乳アレルギーの原因物質となることが多いため、食品アレルギーのある人を考慮した製品をつくる際は、注意して選ぶ必要があります。
- ソイプロテイン
ソイプロテインは、大豆由来の植物性タンパク質で、必須アミノ酸をバランス良く含んでおり、筋肉の成長をサポートする効果があります。また、女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンを含むため、美容や健康目的での摂取にも向いています。吸収速度はホエイより遅く、体内のアミノ酸濃度を長時間維持する特徴があります。水に溶けにくい特徴がありますが、カゼインと同様に腹持ちが良いので、ダイエット中の置き換え食品としても活用できます。動物性タンパク質を避けたいヴィーガンやベジタリアンの方にもおすすめです。
- 原料選びのポイント
プロテインの原料を選ぶ際は、製造したい製品の効果(筋肉増強、ダイエット、美容、健康維持など)に合わせて種類を選ぶことが重要です。たとえば、筋力アップのトレーニング後にはその効果を促すホエイ、就寝前の持続的な栄養補給ならカゼイン、植物由来で健康重視ならソイといった基準で選ぶと良いでしょう。また、アレルギーの有無や、乳糖不耐症の方を考慮するなら、植物性プロテインを選ぶのも一つの方法です。
主なプロテイン製品
-
粉末(パウダー)
最も一般的な形態のプロテインで、水や牛乳に溶かして飲むタイプです。タンパク質含有量が高く、コストパフォーマンスに優れているのが特徴です。運動後や朝食時など、まとまったタンパク質摂取に適しています。フレーバーのバリエーションが豊富なため、消費者の好みに合わせて選べるのもメリットです。ただし、シェイカー等で溶かす手間がかかるため、外出時には携帯しにくいデメリットもあります。その点について最近では、口の大きいパウチ型個包装に粉末を入れた製品が登場してきており、パウチに水や牛乳を入れてシェイカーなしで飲めるタイプとして利用されています。
-
バー
プロテインバーは、持ち運びやすく手軽に食べられる固形タイプのプロテイン食品です。タンパク質以外にも炭水化物や脂質、ビタミンやミネラルを含み、栄養バランスを考慮した製品が多く販売されています。小腹が空いたときの間食や、忙しいときの食事代わりにも適しているため、そのようなニーズを持つ消費者向けの製品づくりで最適です。また、低糖質にしたり、高食物繊維の成分を含有したりすることで、ダイエット中の方にも好まれる製品をつくれます。
-
液体飲料(ドリンク)
すぐに飲めるプロテインドリンクは、コンビニやスーパーなどでも手軽に購入でき、トレーニング後や外出先での摂取に便利です。事前にシェイクする必要がないため、粉末プロテインよりも簡単に飲めます。ただし、保存のために糖分等を含めなければならない場合があるため、カロリー等が気になる消費者には向いていない可能性があります。
- 錠剤(タブレット)
プロテインを固形化したタブレットタイプは、携帯性に優れ、外出先でも手軽に摂取できるのが特徴です。噛んで食べるタイプや、水と一緒に飲み込むタイプがあり、粉末プロテインのようにシェイクする手間がないため、忙しい方にも適しています。また、匂いや味が気になりにくいメリットもあります。ただし、一回の摂取量あたりのタンパク質含有量は粉末タイプに比べて少なくなることが多いため、摂取回数を調整する必要があります。
- プロテイン製品選びのポイント
プロテイン製品を選ぶ際は、消費者の摂取目的、ライフスタイル、携帯性、成分のバランスを考慮することが大切です。例えば、トレーニング後にプロテインを素早く摂取したい消費者向けなら粉末タイプ、外出先でも手軽にプロテインを摂取したい消費者向けならバーやドリンク、持続的な栄養補給を考える消費者向けならタブレットが適していると言えます。ただ、タンパク質含有量、アミノ酸スコア、またタンパク質以外の栄養素の補給の観点からも含有する成分はよく検討し、ターゲットとする消費者に手に取ってもらえるプロテインをつくることが大切です。
プロテインを作るには?おすすめはOEM製造
プロテイン製品の製造を検討されているなら、OEM(製造委託)がおすすめです。OEMを利用することで、原料調達や品質管理といった煩雑な作業から解放され、開発や販売などのコア業務に集中できます。
OEMメーカーは、専門的な知識と経験に基づいて、最適な原料の選定から調合、製造、品質管理までを一貫して行います。また、設備が整った工場を保有しており、効率的かつ衛生的に高品質なプロテイン製品の製造が可能です。その他、OEMメーカーのノウハウを活用できれば、味や香りづけなどの開発もスムーズに進められます。
このように、OEMを活用することで手間を省きつつ、品質の高いプロテイン製品を市場に提供できるのです。
プロテインの最終製品ができるまでのステップ
OEMでプロテインの最終製品ができるまでの流れは、サプリメントOEMの製品化の流れとほぼ同様ですが、以下にプロテイン製品のステップを詳しく説明します。
お打合わせ
まず、製品化のための要望やターゲット市場、販売戦略について打合わせを行います。目的(ダイエット向け・筋力アップ向けなど)とターゲット(置き換えを考えている女性・筋トレ後の男性など)を決めます。目的に合わせたプロテインの種類(ホエイ・ソイ・カゼインなど)や摂取方法(粉末・ドリンク・バーなど)を選び、OEMメーカーと詳細を決めていきます。
製品企画
市場のニーズやトレンドを踏まえ、味や栄養成分(ビタミン、ミネラル、BCAAなど)、配合成分を企画します。この段階でコストやロット数、パッケージ形態(個包装・大袋など)も検討します。
お打合わせ
試作前に希望の栄養条件になっているか、配合処方の最終確認を行います。アレルギー成分や法規制の確認もこの段階で行います。
試作/製造条件取り
実際にプロトタイプを作成し、味や溶けやすさ、口当たりなどをチェックします。必要に応じて改良を行い、納得のいくものに仕上げます。
最終製品仕様の決定
試作の結果を踏まえ、最終的な配合・風味・パッケージデザイン・表示内容を確定します。この時点で正式な見積もりも決定されます。
資材準備
パッケージやラベル、輸送箱などの資材を準備します。資材の印刷作業もこの段階で進めます。
製品製造
確定した仕様に基づき、本生産を開始します。原料の計量・混合・充填・包装といった工程をOEM工場で行い、厳格な品質管理のもとで製造します。
商品完成
完成した製品は最終検査を経て、基準を満たしていることを確認します。この最終検査はロットごとに行われ、徹底した品質管理が行われます。
納品
完成品の出荷判定がおりると指定の納品先へ出荷されます。
プロテインOEMメーカーの選び方
プロテインOEMメーカーを選ぶ際の重要なポイントについて説明します。
高品質な原材料を手配可能か
プロテインの品質は、原材料の品質に大きく左右されます。そのため、OEMメーカーが高品質な原材料を安定的に手配できるかどうかは、非常に重要な選定基準となります。
ホエイプロテインやソイプロテインなどの主要原料が高品質であることはもちろん、甘味料・香料・ビタミン・ミネラルなどの添加成分も信頼できるものを使用しているかが重要です。信頼できるサプライヤーとの関係を持ち、厳格な品質管理を実施しているメーカーを選ぶことで、消費者に安心して使ってもらえる製品をつくることが出来ます。原材料のトレーサビリティや、必要に応じた成分分析の提供についても確認しておくと良いでしょう。
味の相談が可能かどうか
プロテインは、継続して摂取するため味が重要な要素となります。そのため、OEMメーカーが味の相談に親身に対応してくれるかどうかは、重要な選定基準となります。
豊富な味のバリエーションに対応できるか、希望する味を再現できるか、味に関する専門知識を持つ担当者がいるかなどを確認しましょう。原料に由来する特有の香りや味のマスキング、おいしい香りや味の付与など、納得できるプロテイン製品を作るための工夫ができるメーカーを選ぶことで、競争力のある製品開発が可能になります。
開発製造の実績が豊富か
プロテインOEMメーカーの開発・製造実績は、品質や安全性、技術力などを判断する上で重要な指標となります。
過去にどのようなプロテイン製品を手がけたのか、特定のニーズ(スポーツ向け・ダイエット向け・美容向けなど)に対応した経験があるかを確認しましょう。また、専用の製造設備を保有しているか、独自性の高い製品開発や新技術の導入などにも積極的かなども開発製造実績に関連するのでポイントにすると良いでしょう。
法規制や安全管理の対応は十分か
プロテインを食品として販売するためには、食品表示の適正化や各種法規制をクリアする必要があります。OEMメーカーが食品表示法や食品衛生法などの法規制に精通しているかも選定指標の1つになります。
また、食品安全国際規格「FSSC22000」などの認証を取得しているかどうかも、品質管理の観点から重要です。このような第三者機関の認証を取得しているメーカーであれば、原料の選定から製造・出荷に至るまで厳しい検査基準に基づいた管理を行ってより安心して依頼できます。
サポート体制は十分であるか
製品に関する相談や、トラブル発生時の対応など、サポート体制も取引を継続する上で重要な基準になります。原材料情報、製造工程、品質管理体制など必要な情報を開示してくれるか、迅速で明確なコミュニケーションが取れるか、こちらの希望を汲み取ってくれるか、積極的に提案をしてくれるかなどを確認し、スムーズに協力関係を築けるOEMメーカーを選ぶと良いでしょう。
これらのポイントを総合的に判断し、自社のニーズに最適なOEMメーカーを選ぶことが、成功するプロテイン製品づくりのカギとなります。
まとめ
プロテインは、由来原料の種類として主にホエイ、カゼイン、ソイがあり、それぞれに特徴があります。また、プロテインの製品形態としては、粉末、バー、液体飲料、錠剤などがあり、これらは目的とライフスタイルに合わせて選ぶ必要があります。
プロテイン製品の製造には、OEMメーカーを活用することがおすすめで、原材料の取り扱い、味の相談、開発製造実績、法規制対応、サポート体制などを基準にOEMメーカーを選定すると良いです。ぜひ、信頼できるOEMメーカーをパートナーとし、理想のプロテイン製品作りに取り組んでみてください。